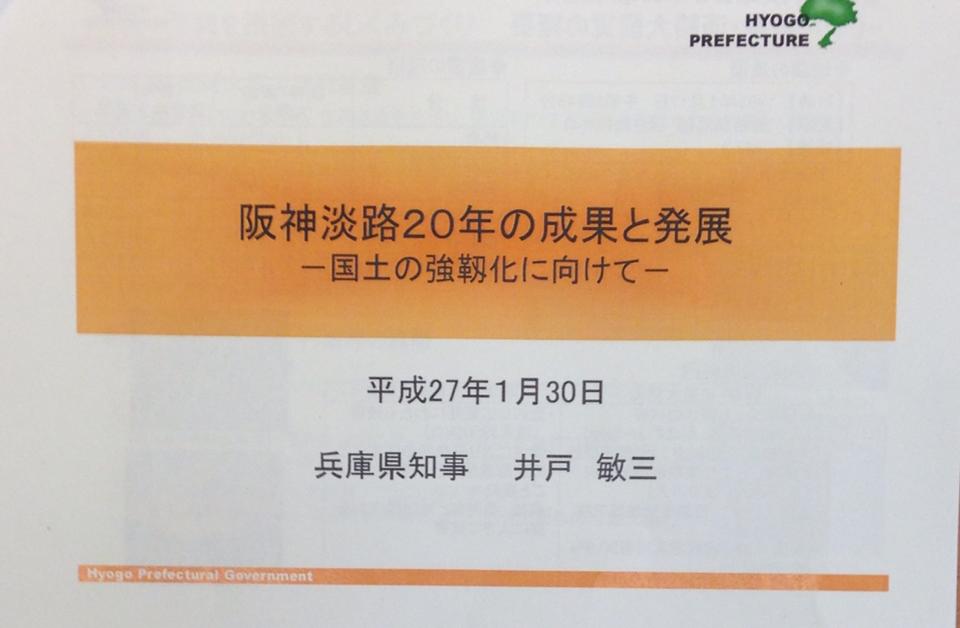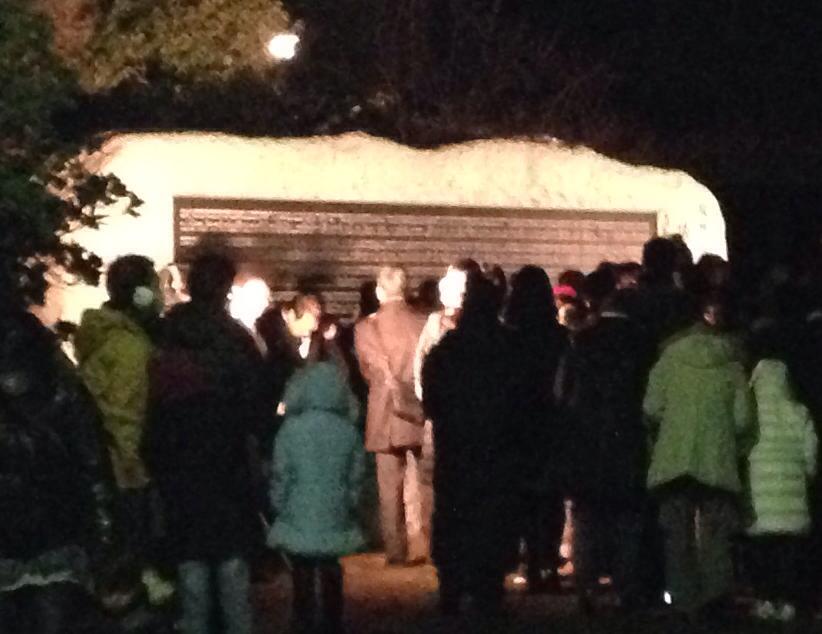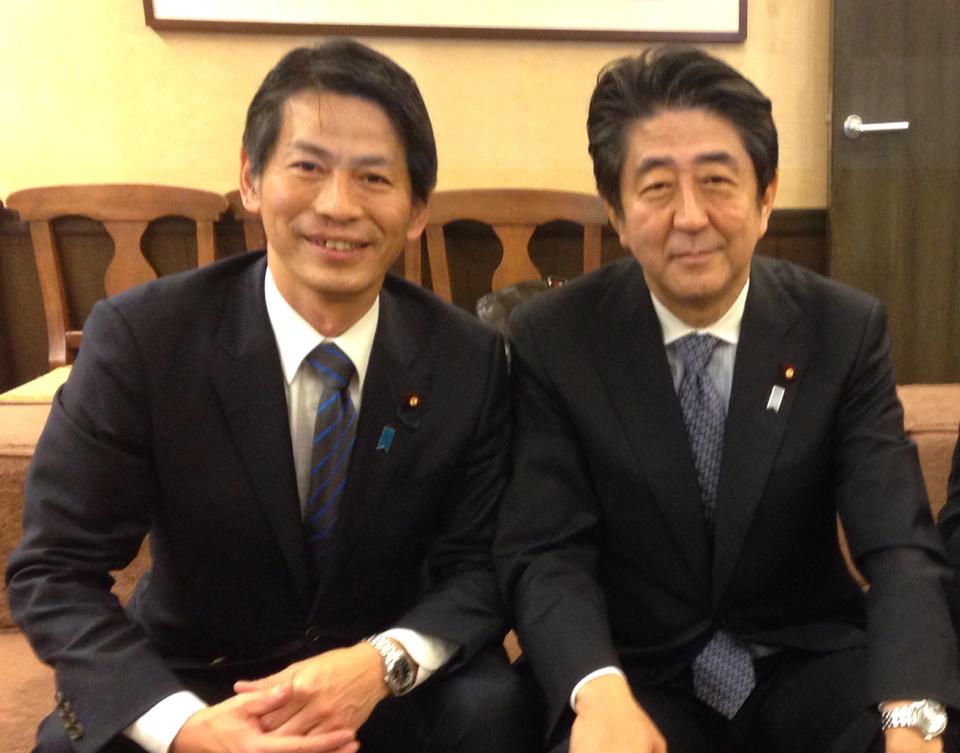|
2015.1.30
今朝の国土強靭化総合調査会は、井戸敏三兵庫県知事をお迎えし、「阪神淡路20年の成果と発展」と題して講演いただきました。
震災後の兵庫県の取り組み、復興の過程を具体的にご説明をされ、最後に兵庫県の要望にまとめる手腕はさすがです。非常に説得力がありました。
2015.1.26
本日、天皇陛下のご臨席を仰ぎ第189回国会が開会。
国会議員有志が和装で登院。朝方雲り空だったのがお出迎えの際には快晴に。 陛下がお越しになる時はいつも快晴で、人知を超えた力を感じます。 今国会では、これまでの財務金融委員会に加え、決算行政委員会、地方創生特別委員会、憲法審査会に所属することとなりました。 選挙戦で訴えましたとおり、日本を元気にするため景気対策、地方創生にしっかり取り組んで参ります。
2015.1.25
芦屋市サッカー協会主催2014AFAアウァーズに出席。
優秀チーム・選手表彰の後、サプライズゲストとして、先日FIFAバロンドール2014授賞式にてFIFA会長賞を受賞されたさサッカージャーナリストの賀川浩さんがご登場。 賀川さんの凄いところは、記念トロフィーやメダルを、会場の参加者に惜しげもなく披露され、大人も子供もみんな群がって手に持ったり、写真をとったりしていて、サインを求める子供たちに囲まれるなど、受賞の喜びをみんなと分かち合うというのはこういうことかと、感銘を受けました。 御歳90歳にはとても見えず、ジョークを交えたスピーチで会場の笑いを誘っていました。 賀川浩の片言隻句
2015.1.25
本日は「越木岩防災の日」。地域住民と小学校、警察、消防、自衛隊が一堂に会し連携して行われる異色の大規模な防災訓練です。阪神大震災の翌年から毎年続けられ今年で20回目。
私も本日は背広ではなく防災服で参加。放水訓練を体験させて頂きました。ホースの装着も、平時から実際に体験しておくと慌てずに行えます。 印象的だったのは小学生の子供たちが整然と避難、集合し、ふざけたり、ダラダラする者もおらず、みんな静かに話を聞いていたこと。大人の真剣さが子供にも伝わるものだと感じました。 はしご車での消防隊員による救出活動、自衛隊員のロープでの降下、消防団員の手際のよい放水活動、白バイ隊員のバイクでのジャンプなどには子供達からも純粋に歓声が上がっていました。 地域の自主防災会主催の訓練でここまでやっているところは聞いたことがありませんが、こうした取り組みが各地に広まればよいと思います。
2015.1.23
本日は、司法修習の給費制の件に関し兵庫県弁護士会の武本会長、藤原副会長が来所。
本件は私も以前より応援させて頂いておりますが、今日は司法養成制度そのものの在り方についても意見交換させていただきました。 大学4年、法科大学院2~3年、卒業後試験にストレートで合格しても司法修習に1年、それでも弁護士事務所でOJTをしないと使い物にならないらしい。 30歳近くになってまだ新人?そんなもの教育機関とは言えないし、制度としても欠陥です。 こんな馬鹿げた制度に人生の貴重な時間をかけるという選択をするのはよほど奇特な人しかいなくなる。 制度導入時に掲げられた、幅広い経験や素養を持つ法曹人材を養成するという理想と真逆の結果を招いている。 こんな(教育)機関に国費を投じているのは納税者として税金の無駄であるばかりでなく、法曹を目指す若者にとっても不幸であり、さらには優秀な若者が法曹を見放しつつあることは社会にとっても不幸なことです。 過ちて改むるに憚るなかれ。根本的な問題としては、法科大学院を受験資格からはずし、参入のハードルを下げて幅広い人が法曹を目指すようにすべき。 その上で法科大学院に意味を見出すとすれば、経営学でいうMBAのように、合格後に本当に学びたい人が、幅広い素養を身につけたり、専門性を深めるなど、自ら通いたくなる教育機関にするべき。 と、いうような話をさせて頂きました。 なお余談ながら、、個々の弁護士さんとお話をしていると本当に素晴らしい方が多いのですが、弁護士会として頂く要望書には「?」と思うことが多く、何故そうなってしまうのか、いつも不思議です。
2014.1.16
本日は日帰りで上京し兵庫県選出の国会議員と谷垣幹事長と意見交換。
私からは、選挙中、年末年始に地元の皆様から頂いたご指摘も踏まえ、自民党が調子に乗って「古い自民党に戻った」と言われることのないようにと忠告申し上げました。 筋の通らないことでも、力のある親分が言えば通ってしまうというようでは自民党自身の信頼を失う。最近、自民党候補に対抗して無所属で出馬し、「選挙に勝てば自民党に入れることになっている」と騙るケースが全国の各種選挙で散見されるが、悪しき前例として利用されないように、と進言いたしました。 自民党が下野した時の反省と、新しい自民党として政権を奪還させて頂いた際の謙虚さを忘れないように我々の世代が声を上げ続けなければいけません。 |