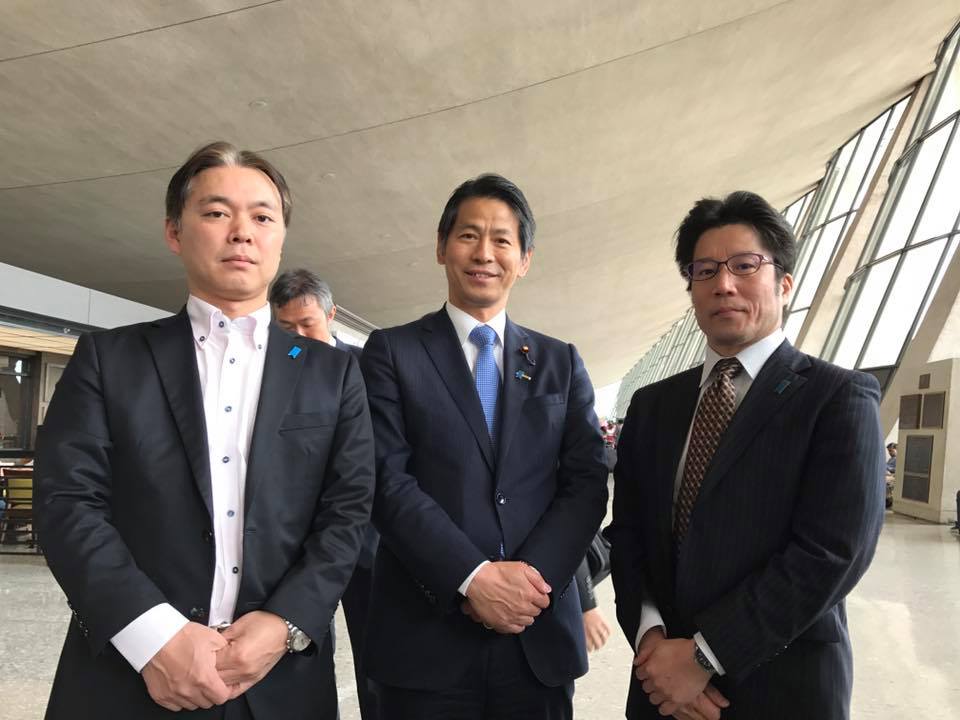|
2018.05.30
日本パレスチナ友好議員連盟。
超党派の議連ですが、あるご縁から事務局長を拝命しております。 本日は駐日代表部のワリード・シアム大使閣下にお越し頂きパレスチナの現状についてお話を伺いました。 親米か否か、親イスラエルか否かという立場は離れて、パレスチナの国家承認を認めるべく国会として要望するための署名を議員各位に呼びかける方針です。
2018.05.30
自民党本部では定期的に各県の物産展を開催していますが、本日は政令都市として初めて神戸市による「食都神戸プロモーションフェア」を開催。
西宮・芦屋はお隣ですが、がっつりとお買い物して消費に貢献しました。
2018.05.29
ヨガ推進議連。
ヨガの効用について講演を聞いた後、体験。 簡単な動作が、意外に言われたとおりにできなかったりして少し焦りました(笑) 短時間ではありますが、気分転換としてこうした機会はとても貴重です。
2018.05.27
めぐみ廣田の大田植え。
普段、当たり前のように炊飯器の蓋を開ければ食べられるご飯。袋に入ったお米は知っていても、そのお米がどうやって作られるか、現在の子供達が実体験で感じることができる機会はなかなかありません。さらに言えば、泥んこになるという機会も少ないのではないでしょうか。 泥にまみれて自らの手で苗を植えることを通じて、お米ができる過程を学び、自然の恵みに感謝するすばらしい行事です。 西宮の廣田神社では毎年恒例の御田植え神事を行っています。長年にわたり伝統行事を守り、暑い中、企画運営をしていただいている実行委員会をはじめ参加された皆様に感謝いたします。
2018.05.27
朝は少林寺拳法演武大会で激励。午後は今津武道会70周年記念大会を見学。
武道を通じて日々鍛錬し、力と技を磨くのは、相手を倒すためではなく、己に勝つために精神を鍛えることにあると思います。 自分を活かすことが他人を活かすことにつながり、それが社会を良くすることに通じると思います。 今津武道会の演武では居合や古武術なども拝見させていただきました。
2018.05.16
コンテナ利用の緊急時医療用施設議員連盟。
可動式コンテナ診療所の現物を議員会館裏の駐車場に運んでいただき議連メンバーとともに視察。大島衆議院議長も参加。 コンテナは、船にも鉄道、トレーラーにも積載可能で、海路のみならず陸路でも広範囲に移動が可能。 医療用設備に加え通信設備を搭載することで、平時は、僻地での検診、遠隔診療などに活用しつつ、災害など有事には被災地に派遣し機能を発揮できる。また、海外の災害にもコンテナごと運ぶこともできる。 無医村対策、地方創生、災害医療、国際貢献など幅広い応用が可能。 実用化、普及活用を後押ししてまいります。
2018.05.11
5月11日、財務金融委員会にて質疑を行いました。
1.日中韓首脳会談の意義について 2.政党交付金について 3.公文書管理について 【日中韓首脳会談】 ・2年半ぶりの日中韓首脳会談。 ・それに続く日中首脳会談では経済金融分野での合意などもなされた。 ・共同宣言では拉致問題の解決についても言及。 【政党交付金について】 国民の血税という点では、あまり触れられないが、新しい政党ができては消えということを繰り返す中での政党交付金の行方も重要な問題。 ・希望の党→国民党→民進党と合併→国民民主党に名称変更。 ・希望の党は4月20日に7億6千万円を受領直後、5月7日に解散。年間30億円が交付される。 ・議員が民進党に移動するだけなら政党交付金は引き継げないが、国民党という一日だけのトンネル政党を作ることにより、議員数に応じた政党交付金が受領できる。 ・政党交付金を引き継ぐための脱法行為ではないか? 【公文書管理について】 ・今般新たな文書の存在が報道され、事実関係を調査中。 ・文書の中身というより危機管理上も問題。 ・悪い話ほど早く報告するよう意識改革を求める。
2018.05.06
最終日は再びワシントンに移動し、シャノン国務次官、ポッテインジャーNSCアジア上級部長らと面談し、あらためて全被害者の即時一括帰国への協力を依頼しました。
その後、記者会見があり、私もコメントを求められたので一言申し上げました。 「拉致問題」「人権侵害」という抽象的な言葉だけでは実感しにくいかもしれませんが、13歳で中学校の部活の後、帰宅途中に連れ去られた横田拓也さんのお姉さん、めぐみさんであり、生後1歳の赤ん坊を残したまま連れ去られた飯塚耕一郎さんの母親、田口八重子さんという、生身の人間がいること。生活を奪われ、将来を奪われ、愛する家族と引き裂かれ、そしてその家族も悲しみのどん底に落とされ、40年以上も未解決なまま、その状況が今も続いている現実を知って頂きたいと思います。 日本国政府はもちろん、与野党を超えて議員も、そして家族会、救う会などの支援団体を含めオールジャパンでこの問題に取り組み、米国はじめ世界各国にも協力を呼び掛けていますが、それを後押しするのは世論の支持です。より多くの人に知ってもらい、後押ししていただけるよう、メディアの皆さんもどうかこのことを報じてください、とお願いをしました。 先ほど全行程を終了し無事帰国しました。 本件についての訪米がこれで最後になることを願い、今後の状況を見守りたいと思います。
2018.05.06
5月3日は朝から国連安保理理事国であるエチオピア、クゥエート、ペルー、アメリカの国連代表部を訪問。
いずれの国も高い関心を持って話を聞いていただき、また支持を表明してくれました。
中でもペルーのハセガワ大使は、時間を延長して熱心にご質問をして下さいました。 そして会談の最後に、「これは奇跡の主(lord of the miracle)と言って、私はずっとこれに救われてきました。」と懐から御守りを取り出され、「しかし、私がこれを必要とする以上にあなた達にはこれが必要だ。(You need this more than I need this.)」と言って横田拓也さんと飯塚耕一郎さんに渡されました。 大使のご人徳に感銘を受けるとともに、国境を越えて思いが伝わると実感しました。
2018.05.04
北朝鮮により一年半にわたり拘束された後、昏睡状態で帰国し、直後に亡くなられた米国人学生オットー・ワームビアさんのご両親、弟さんと会談。
飯塚耕一郎さんから「オットーさんはどんな方でしたか?」と尋ねたところ、「よく聞いてくれました。」と母親のシンディーさんが涙を浮かべながら語ってくれました。 「格好良く、スマートな子で、学ぶことが大好きで、生きる情熱を持っていた子でした」と。母親の愛情溢れる言葉でした。父親のフレッドさんも「しょっちゅう電話で話をしていた。」と。家族から本当に愛されていた青年だったことがよくわかりました。 抽象的に「人権侵害」という言葉だけでなく、拉致もオットーさんの件も、実際に生身の人間が犠牲になっており、その人となりを知り、家族の苦しみに触れることが、この問題の深刻さ、残虐さをより実感することにつながると思います。 父親のフレッドさんは「これまで息子を拐われ沈黙を保ってきたけれども、これからは、彼らが何をしたのか答えさせるための橋渡しとして声を上げていく。」と語られました。 その後、国連でシンポジウムが開催。拉致被害者家族の横田さん、飯塚さん、特定失踪者家族の生島さん、脱北者のチさん、ワームビア夫妻と人権団体 、国連人権高等弁務官事務所長、朝鮮半島研究者らを交えた意見交換が行われました。 日本の拉致被害者家族と米国の犠牲者の家族が参加するということもあり、地元メディアも多数取材に来ていました。 この問題をより多くの人に知ってもらうことが拉致被害者の帰国を含めた北朝鮮の人権問題解決の後押しになると考えます。
2018.05.03
元国務副長官リチャード・アーミテージさんと面談。
氏はブッシュ政権下で北朝鮮をテロ支援国家に指定する際、拉致問題をその根拠に明記させるなど、日本人拉致問題に理解がある。 北朝鮮が「拉致は解決済み」と主張することに関しては、「金正恩には、拉致問題が解決したと言う権利は無い。その権利があるは、家族だけだ。」と。 全くその通りで、このフレーズは広めようと思います。 我々、訪米団の活動に対し、マスコミも注目し始めたようで、日に日に取材陣が増えてきている印象を受けます。 拉致問題の存在、そして生身の人間が囚われて家族と離れ離れのまま40年以上が経っているという残酷な現実を、国を超えてより多くの人が知ることが解決に向けた後押しになります。 明日はニューヨークに移り、国連安保理理事国の代表らと面談の後、国連本部にてシンポジウムに参加予定。
2018.05.03
米国国務省、国防総省を訪問。日本担当ジュリー・チャン国務次官補代行代理、ランディ・シュライバー国防次官補らと面談。(国防総省は撮影禁止)
昨年9月の訪米直後にトランプ大統領が国連演説で日本人拉致問題に言及し、日米首脳会談でも必ず議題に採り上げていることもあり、米国政府、議会関係者の間でも北朝鮮による拉致問題の関心が高まっていると実感。 米国でも日本人が考えている以上に、核・ミサイルだけでなく、拉致問題は重要な問題であり、人権・人道上許されないと認識されており、被害者の帰国が実現されない限り問題解決ではないという点について理解が広まっている。 とりわけ、被害者ご家族の生の声を直接聞くことは心に響くようで、全面的に支持すると申し出てくれた。 米朝対話においても、議題に載せればいいということではなく、被害者全員の一括帰国実現が必須であること、くれぐれも、金正恩による、実態の伴わないパフォーマンスに騙されることないよう、大統領への念押しを依頼した。 この他、北朝鮮情報を分析している38ノースのジェニー・タウン編集長、CSISのマイケル・グリーン副所長、北朝鮮人権委員会のグレッグ・スカラトウ事務総長らと意見交換。示唆に富む情報交換ができた。 |